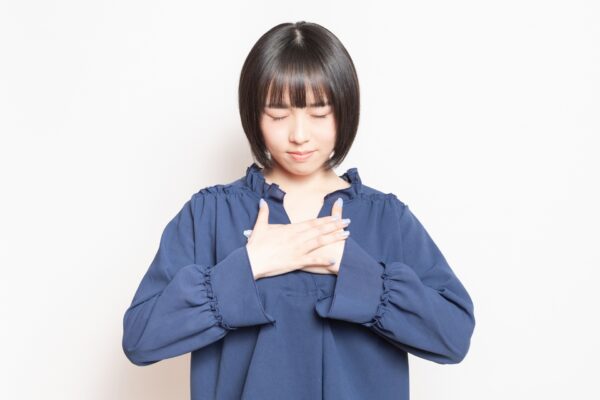【徳を積む生き方】その特徴と効果・行動までを分かりやすく解説してみました

「徳のある人」という言葉からは、何らかの品格が感じられます。
そしてそれは、私たちが目指す理想像といってもよいでしょう。
この記事では、徳を積む生き方とはどういうものなのか、その効果とは、またその行動とはどういうものであるか。
見た目だけでは分からない心の内面まで解説してみました。
きっと迷わずに徳を積める行動ができるようになれるでしょう。
目次
徳を積む生き方をする方法
徳を積む生き方とは、他の人のお役に立つために自分は何ができるかを考えるところから始まります。
人にはそれぞれ才能や環境に違いがあるので、自分の得意分野でお役に立つことを考えるのがよいでしょう。
また、自分のことしか考えてなかったり、見返りばかり求めている行動には、敬意を持てないので、「徳」とは無縁になるので注意が必要です。
他の人のお役に立つ方法としては
1. 体を使う
2. 持っている物を使う
3. 知恵を使う
という方法が主なものになります。
体を使って徳を積む方法
体を使ってお役に立つ働きは、私には何も与える物がないと思っている人でも、やる気さえあれば誰でもすぐに始められる徳を積める方法です。
体力に自信があれば運搬、片付け、救助活動。
料理が出来るなら食事の提供などのボランティア活動が代表的なものになるでしょう。
持っているものを使って徳を積む方法
持っているものを使ってお役に立つ最たるものは、募金や寄付が分かりやすいものです。
寄付はお金だけでなく、持っている物や土地などの寄贈や寄進であっても、必要な人がいて、それが多くの人の幸せに繋がるならば立派な徳を積む行為になります。
欧米社会では、「高貴なる者の義務」というものがあり、社会的に恵まれている者はそれに応じて果たすべき義務があるという道徳観があり、多額の寄付がなされていることはよく知られていることです。
知恵を使って徳を積む方法
知恵を使って徳を積むとは、知識を使い教え導く教育的なものになります。
最も尊いものは、幸せになるための正しい生き方を教えてあげることなので、単なる知恵ではなく、それなりの智慧が必要です。
幸せになる方法を知恵を使って「自分さえよければいい」という考えで正当化するものはいくらでもあります。
それを分けるには、単なる知恵ではなく、しっかりした人生観をもった智慧が必要になってきます。
徳を積むことで得られる効果

徳を積む効果は、言葉のとおり徳(得)があるのです。
お得ないい出来事が起こるようになります。
- 人間関係に恵まれる
- 金銭的に豊かになる
- 仕事が順調に進む
- 家庭環境がよくなる
など、具体的な出来事は人によって様々でしょうが、
- 運が良くなる
- 自信がつく
- 幸せが広がる
という効果があります。
運がよくなる
仏教には、善い行いをしていれば、善い報いがあるという善因善果という教えがあります。
これは、蒔いた種は自分で刈り取るという原因と結果の法則であり、善い行いは善い運気をもたらしてくれるということです。
東洋思想研究家である田口佳史さんが松下幸之助さんに「運を強くするにはどうしたらいいですか」と質問したら、「徳を積むことしかない」と答えられたそうです。
どんな得があるのかは様々だとしても、運の良さは幸せを支える大きな力となってくれるのは間違いありません。
自信がつく
自分の価値や存在意義を肯定できる感情を自己肯定感といいますが、自己肯定感を感じられるには、自分が他の人の役に立っていると感じられることがとても大切になります。
「役立たず」という言葉は自信を失わせる最たる言葉であるところから考えても、お役に立つ行動が自信にとってとても大切な行動であることが分かるのではないでしょうか。
また、自分のことばかり考えて行動している人も、自分の行動に誇りを持てないところがあるので、自信をもつのは難しいものです。
人から見られて恥ずかしくない生き方をしているというところが、自信の根源にあります。
自分の自由に使える時間、才能を自分のためだけでなく、他の人のために役立てようと考えられるところから徳は発生し、そこに誇りが持てるようになり自信となってくるのです。
幸せが広がる
幸せは与えれば与えるほどに増えていくと信じられるでしょうか?
信じられないかもしれませんが、与えたからといって自分の幸せが減っていくわけではありません。
見返りを求めてはいけないと言われることもありますが、見返りを求めてないと思っていても、与えたことを数え上げていれば、返ってこないと損をした気分になってしまいます。
幸せとは、ローソクの炎のようなものと考えてみたらどうでしょう。
自分の持っているローソクの炎で他の人のローソクに火をつけても、自分の炎はなくなりません。
逆に分け与えれるほどに周りが明るくなり、その結果として幸せが広がっていくのです。
徳を積んだ人の特徴
徳のある人の特徴として具体的なものとしての善き性格、人格的な表れはいくつかあるでしょうが、ひと言でいえば、信頼されているかどうかというところではないかと思います。
信頼されている
信頼されている人に徳のない人はいません。
信頼されるだけの行動を積み重ねてきた結果として「徳のある」人としての品格がでてきます。
具体的には
- 自分の都合で人や自分を誤魔化したりしないという(正直さ)
- 与えられた役割を投げ出さない(責任感)
- 他の人を尊重する(礼儀正しさ)
- 優しい眼差しで接する(思いやり)
- 正義を守る(勇気)
などが挙げられます。
どれも高みを目指せば上限はありませんが、日常生活のなかで、周りの人達から「あなたがそう言うのなら、信用しましょう」と言われるくらいの信用は得ている必要があるでしょう。
徳を積む行動
徳を積む行動とは、自分のことばかりを考えての行動ではなく、公の中にある自分として、何ができるかを考えた行動になります。
外から見た行動は同じであっても、自分にとって損得でする行動ではなく、心意気の問題が徳を積む行動になるかどうかの差になってくるといえるでしょう。
- 公共の場を掃除する。
- 困っている人を助ける。
- 寄付をする。
という善い行為であれば、感謝されれば動機など関係ない面もあります。
しかし、
- 自分の評価を高めるために公共の場を掃除する。
- 相手を支配するために困っている人を助ける。
- 見返りを得るために寄付をする。
等であればどうでしょう。
見た目は同じ行為であっても、動機が不純であれば、その行為を続けていけば社会に悪影響を与えることもあります。
これでは、徳などは生まれません。
徳を積む行動はその動機によって左右されますが、純粋な思いで行動できれば、お役に立つ行動すべてが徳を積む行動になってくるのです。
徳を積む意味

徳を積むとは人に対して善い行いを重ねていくことであり、そこには自己犠牲的な面があります。
自己犠牲的な面があるので、そこまでして徳を積む意味が分からないという人もいるでしょう。
実際のところ全ての自己犠牲を喜んで出来るわけではありませんが、自分を犠牲にしてまで、守りたいもの、または信念とする生き方があるから行動できるという面があるのです。
分かりやすいところでは、家族のため、子供のためというものがあります。
たとえ我慢しているところがあるとしても、我慢以上の喜びがあることを知っているのではないでしょうか。
もちろん、我慢していることで、家族に八つ当たりしていてはいけませんが、自分がよければという生き方ではとうてい味わえない大きな喜びがあります。
このように、徳を積む意味は自己犠牲とも見えるけれども、自分の事だけでなく他の人の幸せを考えることで、幸せが拡大していくところにあるのです。
徳を積むスピリチュアル的な面とは
徳を積むスピリチュアル的な面としては、積み上げた徳は来世に持ち越すことができると考えられるところです。
仏教には、カルマ(業)の法則というものがあり、前世の善悪の行為によって現世に受ける報いが変わってくるとされています。
しかし、生まれてくる環境に関しては、徳があるから恵まれた環境が得られるとは限りません。
環境に恵まれていることが徳を積んだ結果としてあるのではなく、より徳を積める環境を与えられると考えられます。
環境の良さはひとつの条件でしかありません。
環境に恵まれていれば、よりお役に立てる立場にあるので、さらに多くの徳を積む人もいれば、恵まれた環境に甘えて、徳を積む行為を怠ってしまうケースもあるでしょう。
逆に、環境に恵まれてなくても、環境を恨むことなく徳を発揮して歴史に名を残している偉人の存在もあり、私たちに勇気を与えてくれます。
徳を積む意味はそれによって人格が向上し、人間として成長していくところであるならば、生まれ変わりを通して永遠の向上の可能性があり、その過程でより大きな幸福感を味わえる。
つまり、前世の徳をどのように活かすかで、あなたの徳はさらに磨かれるようになっている。
これが、徳を積むスピリチュアル的な面になります。
陰徳を積む生き方
陰徳とは、人に知られなくても善い行いを積み重ねていくことを言い、人に知られる善い行いを陽徳と言っているようです。
陰徳と陽徳の違いは、人に知られるか知られないかというところで判断されているところが多く、人に知られないところでする陰徳のほうが、徳が高いとされています。
しかし、実際のところは人に知られようが知られまいが、人の評価を気にしない善行ならば陰徳と変わらないのではないかと思います。
例えば、マザーテレサのしてきた活動は人に知られずに行える性質のものではありません。
マザーテレサが人に知られることなくひっそりと陰徳を積んでいては、救われる人も救われなくなってしまいます。
人に知られようが知られまいが関係なく、人の評価など全く求めていない善行であれば、それは陰徳に劣らぬ価値があるのではないでしょうか。
陰徳を積む利点
経済的に恵まれている人などは、高貴なる義務として人知れず感謝の思いと共に寄付行為をされていることはよく知られています。
有名人であれば、何かの折に名前が公表されてしまうこともあるでしょうが、それを望んでいる人は少ないでしょう。
それは、人は褒められれば嬉しくもありますが、褒められすぎるとどうしても得意になって自慢したくなってしまうところがあるからです。
しかし、身近な人はあまり褒めてくれないので、余計に自慢したくなるというところがあり、これが慢の心と言われる自慢、慢心というもので、成長していくなかで最後まで残る課題になります。
このように人に知られずにいるから転落しない人生を歩めるところはあり、これは陰徳を積む利点であり、それが当たり前になってしまえば、自慢する気もなくなってきて、さらに徳が積めるようになるでしょう。
まとめ
徳を積む生き方として、見た目だけでは分からない徳の積み方を解説してきました。
徳を積む生き方が、そのまま幸せな人生に繋がっていくことに気づいていただければ幸いです。
関連記事